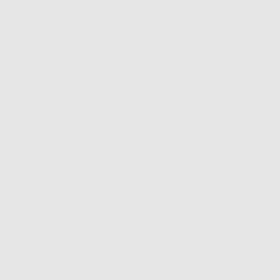「あいち2025」ストーリーズ
作品を知る
セルマ & ソフィアン・ウィスィ
『Bird』―声なき声をきく、絶え間ない反転の舞踊詩
- コラム
- パフォーミングアーツ
地上の重力に抗い、空を自由に飛び国境を悠々と越えてゆく鳥の姿に、人は憧れ を抱いてきた。振付家も例外ではない。『白鳥の湖』や『火の鳥』は力強く優美な羽ばたきをバレリーナに与え、自作の翼で天を目指すギリシャ神話に基づいたモダンバレエ『イカロス』、さらに渡り鳥が空に描く有機的なパターンに着目したコンテンポラリーダンスまで、欧米舞踊史にはいくつもの例が確認されるだろう。しかしセルマ&ソフィアン・ウィスィが鳥に向けたまなざしは、まったく異なる思想から発している。出演は二人の男性と二羽の鳩。ソフィアン・ウィスィとミュージシャンが舞台奥、鳩は舞台両端の止まり木にいる。演奏を伴ってダンスが緩やかに始まり、舞台に広がり、やがてウィスィは鳩の元へ進む。だが彼は鳩の動きを模倣することも、鳩に動きを強制することもない。鳩は人の肩や腕、頭の上を歩み、気ままに飛翔し、予期せぬ場所へ着地する。予測も再現も不可能なこのデュエットにおいて、人と鳥は対等だ。彼らは互いの領域を慎重に探査し、空間と時間が共有されてゆく。
『Bird』は、シャルジャ(アラブ首長国連邦)で生まれた。シャルジャ・ビエンナーレの委嘱を受けたセルマ&ソフィアン・ウィスィは、上演会場となる古い映画館を訪れた。人影の消えた廃墟は鳩の住処となっていた。文明の大きな物語の残骸が無垢な生命のサンクチュアリに再生した光景が、ウィスィ兄妹のなかでコロナ禍を経た世界のイメージと重なった。一羽の白鳩との出会いもあった。ソフィアンはこの鳩を“シャム”と名付け、共に踊ることを発想した……。
チュニジア出身のソフィアン・ウィスィ(1972-)とセルマ・ウィスィ(1975-)兄妹は、首都チュニスの国立学校で音楽と舞踊を学び、共同で活動を開始した。2000年代からダンス、映像、インスタレーション等を複合した作品の発表を始め、ロンドンのテート・モダンの委嘱作品『アルゴスの眼』(2014)以降ベルギー、フランスでも知られ、2025年にはアヴィニオン・フェティバルで『ラアルーサ・カルテット、自分の身振りを発明する自由な身体』を発表している。
フランスで教育を受け、1990年代からフランスを拠点として活動するマグレブ諸国出身のダンサー/振付家(エラ・ファトミ、ナセラ・ベラザら)に対し、セルマ&ソフィアン・ウィスィはチュニジアで、チュニジアの社会的コンテキストにおいてダンスを思考し、実践してきた。チュニスで2007年にアートセンターL’Art Rue(ラール・リュ)、フェスティバルDream Cityを立ち上げ、活動は今も続く。前者は芸術創造と民主主義の諸問題を呼応させる持続的なリサーチの場、後者は移民、政治的社会的抑圧からの解放、人権、気候変動をテーマとするビエンナーレだが、多様な領域のアーティストと地域の人々が思想や経験を交換・共有する機会であることは変わらない。政府の抑圧に対して民衆が立ち上がったジャスミン革命を端緒とする民主化の階梯を人々と共に生き、芸術を媒介とする対話の回路をすべての人に開くことで、二人は“理想の都市(ドリーム・シティ)”の可能性を問い続けている。
こうしてセルマ&ソフィアン・ウィスィの仕事の射程を一望するとき、『Bird』の鳩は人為の対極にある自然の象徴に留まらず、異なる文化を有する他者の象徴として現れるだろう(作品ノートでウィスィはパレスチナの亡命詩人、マフムード・ダルウィーシュの詩業に言及している)。場の記憶に敬意を払い、声なき声に耳を澄まし、ウィスィの身体は鳥、そして観客とムーヴメントによる繊細な対話を紡いでいく。権力や傲慢を手放し、他者の存在を尊重し、同じ空間・時間を共に生きる約30分間のできごとのすべては、一編の詩に似ている。『Bird』は「観客に思索するための空間をそっと差し出す、開かれた招待」だとアーティストは語る。あいちで私たちは何を受け取り、何を思うだろうか?