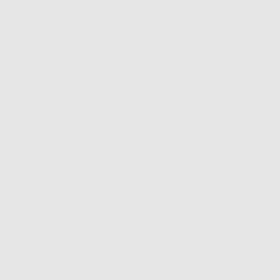「あいち2025」ストーリーズ
作品を知る
インタビュー
アーカイブとしての身体:フォスタン・リニエクラ
- インタビュー
- パフォーミングアーツ
本作品でリニエクラは、彼自身の女性の祖先たちを象った彫像が舞台上に並ぶ中、サン・ラ・アーケストラのヘル・シャバカ=ラのトランペットの伴奏とともに自身の過去を探求する。彼は、タイトルや共演者こそ変われど、何年も同じ作品をつくっているような感覚があるという。
彼の作品は、「リニエクラ」という名の意味を探し続ける営みでもある。それは単なる識別のための文字列ではなく、自分自身、歴史、地理、他者との複雑な関係性への扉なのだ。2018年には、アフリカ博物館(Tervuren)前でモヤ・マイケルと共に『Banataba』を上演したが、そこでも返還、植民地主義による知の断絶、歴史における女性の役割といったテーマが語られていた。それらは5年を経た今回の新作にも通底している。
リニエクラは、自分を振付家やダンサーではなく、「ストーリーテラー(語り手)」と称する。
世界的に評価されるキャリアを築いた彼だが、コンゴ民主共和国の首都キンシャサから飛行機か水上交通でしか訪れることができない故郷キサンガニに「スタジオ・カバコ(Studios Kabako)」を設立した。結局、彼は亡命先からの物語には興味がないのだ。スタジオ・カバコは単なるダンスカンパニーの拠点ではなく、若いコンゴ人クリエイターたちの芸術的実験と交流の場である。想像力を育む空間をつくることこそ、彼の芸術的使命の核心なのだ。
2020年には、『My body my archive』の初期バージョンをロンドンのテート・モダンで上演する予定だったが、コロナ禍で実現がかなわなかった。身体が世代を超えたトラウマや植民地主義による知の分断とどう向き合うかを描くこの作品は、現在においても非常に重要な意味を持つ。最近では、ベルギー議会のコンゴ調査委員会が植民地支配への謝罪を巡る意見の対立から、実質的には何も進展をもたらさなかった。一方で、コンゴ東部では無数の命を奪ってきた紛争がいまだ続いている。リニエクラの活動は、過去と現在の繊細な接点に位置している。彼自身が語るように、歴史が答えを出せないなら、芸術家が見いだすことができるだろうか?
──今回上演する作品は『My body, my archive(マイ ボディ・マイ アーカイブ)』と題されています。身体をアーカイブと捉えるという考え方にたどり着いた経緯を教えてください。
植民者が到来する前、私たちの民族には文字はありませんでした。仮面、イメージ、歌、物語などの方法で、経験や知識を記憶・継承の手段としてアーカイブしていたのです。けれども、植民地化とともにそれらのアーカイブのあり方は分断され、植民者により異なる記録方法を押し付けられました。つまり私たちが歴史を知ろうとするとき、アーカイブについて問おうとするとき、それはまったく異なる見方をしなければならないということです。しかも、そうした植民地化以前のアーカイブの多くは破壊され、残されたものも国外に持ち去られてしまいました。私はよく、コンゴを砕かれた鏡に例えます。その鏡の破片は世界中に散らばっているのです。ベルギーのテルビューレンにあるアフリカ博物館は、その鏡の破片の多くが収められている象徴的な例です。コンゴでこのようなアーカイブに触れることができないなら、私たちは何をよすがに自らを理解することができるのでしょうか? たとえ植民地時代のアーカイブを見ることができたとしても、それは征服者のアーカイブなのですから、私たちの知識の基盤とはなり得ません。このことに気付いてから、私は「自分の身体もまた、ひとつのアーカイブでないか」と考え始めました。今日生まれた赤ちゃんでさえ、過去の世代の経験をどこかに宿しているのではないか? そうであれば、ダンスは、自分の身体を探求する手段の一つになり得るのではないか? 重要なのは、身体に動きを指示するのではなく、身体が自然と語り始めるような状態に導くことです。その語りは、過去の世代の経験から表出される言語なのでしょう。私がその言語を理解できるかはわかりません。けれど、私は少なくともこの問いを立てたいのです。
公的な記録にアクセスできないこともあり、自分の家族のアーカイブに目を向けるようになりました。ここ数年、母方の祖父の村を訪れて、家族の歴史を学んでいます。家系の歴史について語るとき、まず気づくのは、伝えられるのは男性の名前だけだということです。そこで私に問いが生まれました。『女性たちはどこにいるのか? なぜ彼女たちのことは語られないのか?』やがて気づいたのです――私の祖母たちもまた、私の一部ではないかと。私は彼女たちの“息子”なのだから。踊ることは、私の内にいるその女性たちを呼び覚ます手段になりうるかもしれない。私はレンゴラ族の彫刻家Gbagaに依頼して、自分の一族の女性たちを表現してもらいました。レンゴラの文化では、彫刻によって祖先を甦らせることができるのです。「歴史が答えをくれないのなら、芸術家が答えるのかもしれません。」
──コンゴ民主共和国の歴史は、身体への暴力の歴史だ」とあなたは言っています。このように暴力にさらされてきたコンゴの身体は、どうすれば自由になれるのでしょうか?
実は、コンゴに限らず、歴史そのものが身体に対する暴力のかたちの変遷として読み解けるのではないでしょうか。ヨーロッパ社会においても、ほぼすべての社会制度や政治制度は、身体を制御するための仕組みのように思えます。たとえば宗教もそのひとつであり、身体を抑制する手段といえるでしょう。たとえ手を切り落とすとか、拷問する、殺すといった文字通りの暴力がなくても、西洋社会においても、身体を抑圧し制限する別のかたちの暴力が存在し続けています。
コンゴにおいては、その暴力は文字通りの意味でも語れます。たとえば、女性への性的暴行が戦争の武器として使われたり、人々が拷問され、命を奪われたりしています。
それでも、その中で身体は、あるかたちで、つねに堕落や拘束への抵抗を続けているように見えるのです。実際、コンゴの文脈でも、身体は決して完全に抑え込まれることはなかった。むしろ身体こそが、最後の砦なのです。暴力や抑圧に抗う最前線です。
そして、身体が抵抗する手段のひとつが“ダンス”です。多くのコンゴのポピュラーなダンスは、ストリートで生まれました。ストリートでシェゲ(コンゴ民主共和国の路上生活の子どもたち)が即興で踊っている時、そこには自由があります。彼らの身体は、服従を拒んでいるのです。最終的には、私たちが身体を助けるのではなく、身体こそが私たちを助けてくれるのだと思います。
──ダンスは「忘却」の手段にもなりえますか?
いいえ、それは決してありません。忘却は決してあってはならない。むしろ身体を活性化させ、記憶すべきなのです。なぜなら身体が記憶すれば、私たちの祖先が編み出した“生き残りの戦略”も思い出すことができるかもしれないからです。
暴力が繰り返される世界だからこそ、祖先たちが身体に埋め込んだその戦略を忘れてはいけないのです。
──あなたの作品では、植民地主義的な文字の記録と対比されるアーカイブのあり方として、仮面や彫刻などが重要な役割を果たしています。返還(Restitution)というテーマも繰り返し現れますね。
私が問いかけたいのは、知識人や政治家による議論を超えたところでの“ 返還”とは何なのか、ということです。たとえば私の祖父の村であるバナタバにおいて、返還はどのような意味を持つのでしょうか?その地域に住む人々にとって、返還が単に「物の返却」というだけでなく、自らの歴史を取り戻す手段になり得るべきです。私にとって返還とは、単に仮面や彫刻そのものに留まりません。重要なのは、いま、バナタバで育つ若者たちが、そのような仮面や彫刻の作り方を知っていること。そして、今日の歴史をそれらに刻み込む方法を知っているかということです。それは、物を返却して博物館に収蔵するよりも意味のあるものとなるでしょう。ヨーロッパで長くそうであったように、博物館において、仮面や彫刻のアーカイブは囚われた状態に戻ってしまう。物の返却も価値がないとは言いません。しかし、博物館を訪れるためだけにキンシャサまで旅行できる人は限られています。大切なのは、知識の返還、地域社会における返還です。私たちが、先祖がしてきたようなアーカイブの方法を再び身につけたとき、何を生み出せるでしょうか?現在は映像や他の技術を通じてアーカイブを残すこともできる時代です。それらの方法を組み合わせたら、どのような新しい 可能性が生まれるでしょうか?
──あなたは、首都キンシャサの一極集中への批判を実践的に体現されています。2006年には、スタジオ・カバコをキンシャサから北東部のキサンガニへ移転されました。キサンガニはあなたの故郷ですが、同時に「中心」を問い直す行為でもあったのでしょうか?
ダンスにおいても、「中心と周縁」という空間の概念がありますが、これは植民地主義の遺産として私たちに受け継がれたものです。いま私たちが使っている劇場空間も、ヨーロッパによる設計です。ルネサンス期にイタリアで発展した「正面舞台」ですね。もっともよく観劇できるのは「王の席」――つまり権力者の視点であり、それを中心として劇場全体が設計されている。同時期に、絵画や地図における“遠近法”という概念も生まれました。それは、ヨーロッパが世界を征服しようとしていた時代です。自らの視点を、世界に押し付けようとしていた。地図は世界を狭め、劇場建築もまた一方的で支配的な視点を再生産する。でもやがて私たちは、他の視点も可能であると気づいたのです。「王の席」からの視点は、数ある視点のひとつにすぎません。中心は固定される必要はなく、部屋にいるダンサーの数だけ中心があるのです。
その気づきを得たとき、私はキサンガニも「世界の中心」になり得ると感じました。まさにそうです。キンシャサも、キサンガニも、シドニーも、東京も、パリも――どれもひとつの点にすぎない。どの点も他より重要というわけではありません。これが私の基本的な哲学です。コンゴ民主共和国は非常に中央集権的な国家で、キンシャサの外で生きることは不可能だと思われがちです。私にとって、キサンガニにスタジオ・カバコのようなプロジェクトを立ち上げることは、中央集権への抵抗でもあるのです。キサンガニであれ、どこであれ、自分自身の「世界の中心」から人生を築くことができると受け入れさえすれば、どこでも生きることは可能なのです。
──あなたは作品をキサンガニや、祖父の村であるバナタバでも上演されていますね。ヨーロッパでの上演とはどのように違いますか?
現代アートは、世界のどこでも「奇妙な存在」として受け止められています。私にとっての問いは、「この奇妙な存在に対して、観客が自分を重ねられる可能性はあるか?」ということです。
私がバナタバで作品を上演して、人々がそこに何かを“感じ取る”ことができるか――たとえ完全に理解されなくても、何かに触れることができるのだろうか?」
ヨーロッパとコンゴでの上演の最大の違いは、コンゴの観客は私を見るとき、西洋美術史の文脈を持ち込まないことかもしれません。彼らは、私の作品を「あのヨーロッパ人アーティストの誰々に似ている」などとは比較しません。知識人たちは時にそうしますが、「アフリカ的ではない」などという批判は、実は植民地的視点の再生産にすぎないのです。
でも多くのコンゴの観客は、そんな枠では見ません。これはアフリカ的か?などとは考えない。ただ「今」を生きているのです。もし作品が響けば、彼らはその場で反応してくれます。終演まで待つ必要はない。私にとって今後での上演は、ヨーロッパで上演するのと同じように必要なことです。そもそも植民地支配とは、私たちを「小さなヨーロッパ人」にしようとする試みでした。そしてある意味で、それは成功した。私もまた、ある意味でヨーロッパ人です。私は、コンゴでもヨーロッパでも、人とつながることを求めているのです。
──ヨーロッパの観客は、あなたの作品に“アフリカらしさ”を期待するのでしょうか?
20年前、あるフランスの新聞が私についての記事を出しました。
結論は、「フォスタン・リニエクラには才能があるが、それを『アフリカ人になろうとしない』ことで無駄にしている」というものでした。いまだに、「アフリカ人であること」がどういうことか知っていると主張する人たちがいるようです。私は、まさに「アフリカ人であるとは何か」が分からないからこそ、今の活動を続けているのです。アフリカの人々は、常に自分自身を“再創造”しています。言語も、生活様式も、常に再設計され続けている。
いまやその外部要因は中国から来ることもありますが、それすら創造的に受け入れたり拒否したりしています。常に変化し続ける創造のプロセスなのです。
だからこそ、私はそういった期待や偏見に対して闘うことにエネルギーを費やすのをやめました。むしろ、自分の身体、自分の名前という非常に個人的な場所に作品を戻していく。それが、私という「人間」としての出会いを可能にすることを願っているのです。もちろん私は自分の背景を完全に受け入れていますが、それ以上に、まず「人間」として出会いたい。
もしかすると普遍的であるということは、極めてローカルであるということかもしれません。私たちすべてが身体を持っている。「身体の中にいる」という、ただそれだけのことが、普遍性の始まりになるのです。
もし自分の足元をほんの少しだけ掘れば、地下水脈にたどり着くかもしれない。どこを掘っても、誰でもそこにたどり着けます。それは、つながるということ。頭でつながるのではなく、呼吸や足元でつながるということです。すべての人が木のように根を持っています。
すべての木々が、それぞれの場所に立っていて、でも互いに通じ合っている。森全体が、通じ合っているのです。
『My body, my archive』(2023年、Bozar、Kunstenfestivaldesarts)
※本稿は『rekto:verso』に掲載された記事を許可を得て一部抜粋し、翻訳した。
引用元 https://www.rektoverso.be/artikel/the-body-as-archive-interview-with-faustin-linyekula